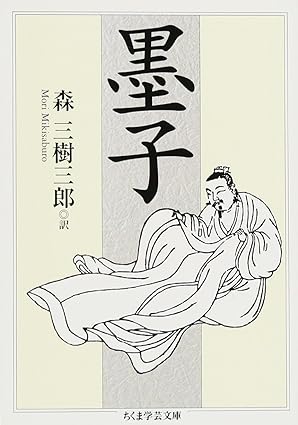平和志向の源流には墨子の「兼愛」
春秋・戦国時代には多種多様な思想家、言論人が活躍し、大物はそれぞれに一派をなした。諸子百家と呼ばれるその中で、もっとも名高いのは儒家の始祖、孔子だろう。彼の教えを弟子がまとめた『論語』はいまだに概説書や啓蒙書の出版が後を絶たないロングセラーだ。
次いでファンが多いのが老子や荘子(老荘思想)。不世出の武道家にして俳優だったブルース・リーは老子を愛読していた。
けれども平和志向の源流をめぐる旅においては、紀元前5世紀に活躍した墨子と、彼がおこした墨家が必修科目になる。
戦国時代の魯の国に生まれた墨子こと墨翟(紀元前470頃~390頃)は、はじめ儒学を学んだがしっくりこなかったらしく、長じて自身の主張を展開するようになった。後に弟子たちがその教えを(自分たちの解釈や主張もこみで)まとめたのが『墨子』だ。欠落や、章題しか残されていない部分も多いが、思想の骨子は幸いしっかり把握できる。
墨子の平和志向は、「兼愛」と「非攻」の2語に集約される。
兼愛(『墨子』巻4)とは分け隔てのない愛を指す。孔子がおこした儒学にあっては、愛に優先順位のようなものが決められてしまっていた。たとえば自分の親より他人の親に愛を注いだら不孝とされるし、自国より他国を想ったら不忠とされるだろう。
それはまあ、忠だの孝だのといった大層な言葉を使わなくとも、直感的、本能的に「おかしい、悪い」と思われるかもしれない。その上、当時は身分差の意識が強かった。
だが、片方を愛したらもう片方を愛せなくなる、という窮屈な考えこそがいけないのだ。どちらも愛せばよいではないか。いや、愛すべきなのだ。
「一人の男が自分の家ばかり愛し、他の家を愛さなかったら、他の家を乱して自分の家だけ得しようとするだろう。諸侯が自国ばかり愛し、他国を愛さなかったら、他国を乱して自国だけ得しようとするだろう」
「人の国を自国のようにとらえることができたら、誰が攻めこむだろう。これができたら、家と家との争いも、諸侯が互いの国を攻め合うのも、起こりようがないのだ」
(いずれも第15節より著者意訳)
ここではすでに「兼愛」が戦や争いをなくす力を持つ可能性が示唆されている。なお、「兼」と対義の関係になるのは「別」と呼ばれる。すなわち差別の「別」だ。
そして当時の世は別愛が主流だった。論理的な性格で貫かれた『墨子』は、いちいち自説に対する反対意見を想定し、記し、それに反論を加えてゆく。思考のシャドウボクシングだ。
兼愛のすすめ、に対する反対意見としては「そりゃできたらいいけど、難しいでしょ、無理でしょ」といった論旨が多い。これに対し墨子は「いや、できる。いにしえの聖王がやってらしたのがまさに兼愛なんだから」と反論する。
考え方そのものを非とする意見は「兼愛すると“孝”のさまたげになるのでは?」くらいだ。これに対しては「他人の親をも愛すると、めぐりめぐって自分の親にもかえってくるのだから孝は保たれる」というような返事をしている。孝なんて考えがそもそも間違ってる、とは考えていないのだ。その意味で、儒学に真っ向から対立しよう、という主張ではない。