虹のように紡がれる七色の物語
今回のキーワードは宇宙への憧れ。加納朋子さんの新作『空をこえて七星のかなた』は七篇からなる連作小説です。等身大の人間が直面するさまざまな問題が意外な形で解決していく驚きを味わってください。各話が北斗七星のように揃ったとき、意外な真相が明らかになっていきます。作品の狙いや、物語に込められた加納さんの思いを伺ってみました。
聞き手・構成=杉江松恋/撮影=三山エリ
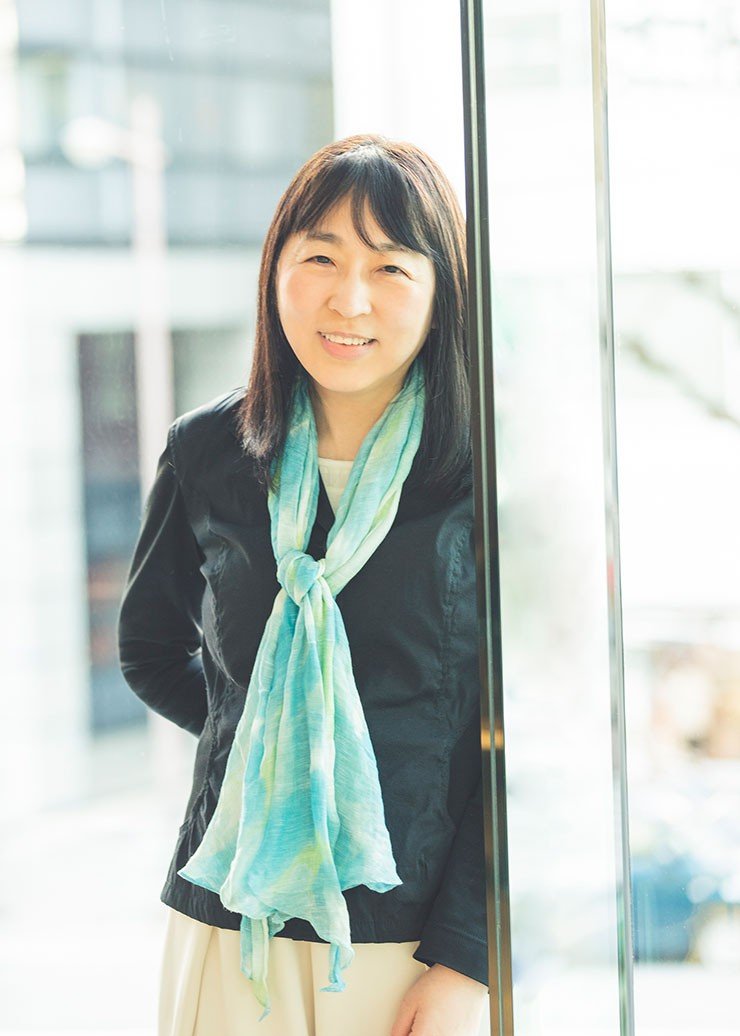
宇宙への憧れ
―― 非常におもしろかったです。全七話はすべて『小説すばる』初出とのことですが、連載としては第一話の「南の十字に会いに行く」だけが二〇一七年六月号でちょっと早いんですよね。
はい。「南の十字に会いに行く」は宇宙をテーマに、ということで書いた短篇でした。その後何か新しい連載を、というご依頼をいただいたときに、そこで描いた物語の先を自分でも知りたくなって。それが構想の始まりでしたね。
―― 宇宙への憧れが全体の共通項ですが、ご自身が関心をお持ちなんでしょうか。
第二話の「星は、すばる」とも重なってくるんですけど、私は小さい頃からかなり視力が悪くて、みんなが「綺麗ね」と言っている星をよく見ることができなかったんです。その悲しさもあって逆に憧れが募りました。都会ではもともと星は見えませんし。私が若かった頃住んでいたところにプラネタリウムがあって、通うのが好きでした。そのあたりから星に関する写真集や文献とかを読み漁るようになりまして。とても好きだったのが林完次さんの『宙の名前』(角川書店)という写真集です。近い話ですと、小惑星探査機「はやぶさ」に心魅かれました。ちょうど私が急性白血病で入院していて、いちばんつらいときに地球に帰ってきたんです。それでとても思い入れが深くて、翌々年JAXA(宇宙航空研究開発機構)の相模原キャンパスで開かれた「はやぶさ」プロジェクトに関わった方の講演にも、足を運んで聴きに行きました。会場の横にプラネタリウムがあったんですけど、そこで「はやぶさ」の映画を観て大号泣してしまって。パッと電気がついたときに、隣に大学生ぐらいの女の子がいたんですけど、彼女も泣いていて、二人で目を合わせて笑った記憶があります。
―― 加納さんの中で、宇宙に関する思いは特別なものになっているんですね。
はい。いつもは大事なところに封印していて、時々開けて、綺麗だな、と見るような感じです。最近はネットで星雲の画像なども見られるようになってきていますが、見ているとその中に吸い込まれそうになります。
―― 本書には全体を通して読むことで浮かび上がってくる、ある大きな物語があります。この着想はどういう形で浮かんできたんでしょうか。
「南の十字に会いに行く」は、もともと童話的な話になるような形で考えていたものなんです。それに続く話を書くときに、第一話の物語を分解して、その構造を連作の全体で繰り返してみたいということを考えました。そこが出発点でしたね。
―― おもしろいですね。先に書かれた短篇を第一話として、連作全体を規定するものになるという。ちょっとしたフラクタル構造じゃないですか。この連作は、どの話もミステリー的なプロットを応用した物語になっていますけど、同じような話が一つもないのが特徴ですよね。絶対にプロットが重ならない。贅沢な連作だと思います。
ありがとうございます。
























