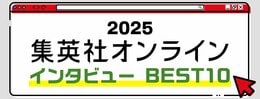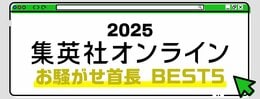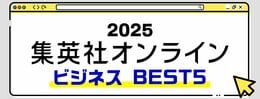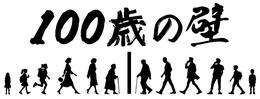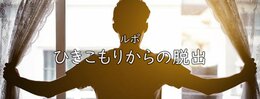今や「絶滅危惧種」に近いさんま
次に、生鮮魚介で値上がりが目立つ品目が何かを見ていこう(図表1-2-2)。同じく過去10年間の物価変動を、総務省「消費者物価」を使ってみたものである。1位は、さんま(上昇率135・6%)である。秋の味覚のさんまは、4年連続で不漁である。世界的にも不漁なことから、もはや入手困難な魚になった。絶滅危惧種ではないが、それに近い。

北海道東部から三陸沖の漁場で、海水温の上昇のためにさんまがいなくなったと言われる。地球温暖化の影響がここにも現れている。このほかにも、公海上での、中国と台湾の大型漁船が乱獲しているという海外情勢が絡んでいる。
2位はいか(上昇率108・0%)、3位はいくら(同93・8%)、4位は塩さけ(同91・6%)、5位はさけ(同72・3%)、6位はししゃも(同70・0%)と続く。
逆に、あまり値上がりしていない種類を探すと、いわし(18・2%)とあじ(12・8%)が10年間で見て比較的安定している。それでも10%以上は上がっている。
上昇ランキングの上位を詳しく見てみよう。2位のいかの値上がりは、さんまと同様に不漁が原因とされる。漁獲量は、2015年頃から2013年比で50~66%も減った。海水温が変化し、稚魚の生育環境が悪化したことも影響しているようだ。いか釣り船の燃料費も高騰している。
いくら、塩さけ、さけは、同じく不漁が原因だ。ロシアのウクライナ侵攻で、ロシア上空を通って空輸されるノルウェー産サーモンが空路の変更を強いられ、輸出量が激減している。代わりに、カナダ、チリなど別の産地への需要が高まった。
こうした水産資源の減少は、地球環境の異変が大きく関係している。「不漁」という表現は、何か「今年はたまたま例年よりも獲れない」というニュアンスを与える。しかし、地球環境の異変が不可逆的なものであることを考えると、来年以降も漁獲量は不安定である可能性が高い。地球環境問題を甘く見てはいけない。