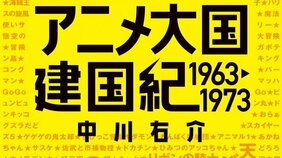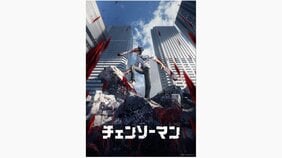不可能な数字
手塚治虫のアトムシリーズ第1作となる『アトム大使』は、光文社の「少年」1951年4月号から連載が始まった。まだ「SF」という言葉になじみがないので、「長編科学冒険漫画」と銘打たれていた。
舞台は「50年後の東京」、つまり21世紀初頭という未来だ。当初は具体的な年月日は特定されていないが、後に2003年4月7日にアトムは誕生したことになる。いずれにしろ、1950年代の子どもにとっては、遠い未来だった。
天才科学者・天馬博士はひとり息子のトビオを交通事故で亡くし、その子そっくりのロボットを作った。しかしロボットなので成長しないことで憎むようになり、サーカスに売り飛ばしてしまったという設定だ。『アトム大使』でのアトムは、地球とそっくりの天体から来た地球人そっくりの宇宙人と、地球人との交渉役として活躍した。
『アトム大使』は単独の作品のつもりで描かれていたが、アトムの人気が出てきたので、52年4月号から『鉄腕アトム』として、改めて連載が始まった。以後、数回でひとつの第5章『鉄腕アトム』革命前夜──エピソードが完結する形式で、連載が続いていた。1962年の時点で12年目になる。
アトムは外見は10歳くらいの男の子で、7つの力が備わっていた。
①電子頭脳はどんな計算も1秒で正解を出せる。
②ジェット推進器で空を自在に飛べる。
③耳の力を1000倍にまでできる。
④世界60か国語(100か国語、160か国語の設定もある)で会話ができ宇宙人とも話せる。
⑤暗がりでは目がサーチライトとなる。
⑥10万馬力のパワー。
⑦お尻からはマシンガンを発射できる──この7つの力を駆使して、アトムはさまざまな事件を解決し、さまざまな敵と闘ってきた。
そのアトムの活躍ぶりを動く絵にして、テレビで見せるのだ。子どもたちが喜ばないはずがない。