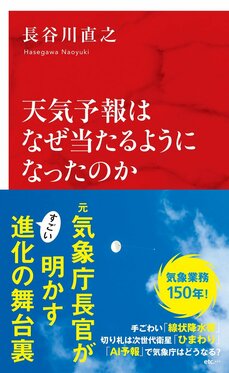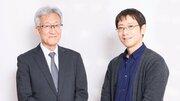AI予報でいいのか
今後、このAI予報がどこまで進化するかはわかりませんが、これまでの数値予報の進化のように、よりきめの細かい予報を、より正確に、そしてより先まで予報できるようになっていくと思います。日本の気象庁でもAI予報の導入が進められると思います。
気象の関係者なら、それでいいのか? と疑問を投げかけたくなるでしょう。
一般的にAIによる予測は、理由が示されないこと、過去に経験していないことは予測できないことなどが弱点とされているからです。予報の根拠を説明できなくなって困るのではないか、過去にないような異常気象は予測できないのではないかといったことが心配になるのです。
それに、これまで何百年も積み重ねてきた物理学やそれに根差す気象学が発展し、ようやく天気予報が当たるようになってきたのに、全部AIでできると言われると、ちょっと面白くありません。
しかし、天気予報の実用の場面では、それでいいのだ、というのが筆者の答えです。普通に生活したり、ビジネスをしたりする人にとっては、理由がどうかということよりも、まずは当たることが大事でしょう。
異常気象の問題も、70年以上のデータを用いて学習するので、それなりの異常気象はカバーしていますし、実際のAI予報のやり方や実績を見ていると、必ずしも過去にないような異常気象を予報できないとは言えないと思います。
写真はすべてイメージ 写真/Shutterstock