舞台は死者と生者の境界
小川 公演後とはいえ、あまり種明かししないほうがいいかもしれないのですが、マックが灯籠を抱いて「ただいま」と言う台詞がありますね。げらげら笑いながら観た最後の最後で「ただいま」と言って帰ってきてくれる人がいる平和な暮らしが、どんなに大事なものかをがつーんと知らされます。
福井 あのシーンの美しさは稽古場では分からなかったんです。劇場で初めて観た時は驚きました。
小川 マックの結婚相手ポールが男性だということに誰も疑問を呈さないで、みんなで「今日はめでたい日だ」と騒いでいるというところから始まるのも印象的です。最初から男女、死んだ人と生きている人、国と国民……、いろんな境界線が破られている。だから、ジェニーを福井さんが演じられて、それが男性か女性かなど気にならなくなる空間が見事に成立している。
福井 それが鄭さんの狙いでしょうね。
小川 以前、鄭さんと対談させていただいたときに伺ったのですが、韓国にはチェサという風習があって、食卓にあふれんばかりに御馳走を並べ、さまよっている死者に振る舞うそうです。鄭さんの作品の主題には誰も合掌してくれる人がいない、さすらっているような死者たちを、舞台上でよみがえらせて、舞台の魔法にかけて自由に動いて無念を晴らしてもらう一面がある。「てなもんや三文オペラ」のパンフレットの中で、演劇評論家の内田洋一さんも、「演劇とは非業の死者に花を送る行いではないかと思うときがある」とお書きになっています。
福井 そうですね。
小川 つまり舞台に立っている方というのは死んでいる、死者でもあるんですよね。舞台上と客席の間には絶対に踏み越えられない境界線があり、観客が舞台上に上がることはできない、やってはいけないことで、観客にとって舞台上にいる人たちは異界の人々です。そういう人たちにひととき異界からこの世に降りてきてもらって、生きているとき言えなかった言葉を生きている私たちが聴いている。舞台とはそんな場のように思えます。
「レ・ミゼラブル」のラストなどは、本当に死んでいる人ばかりが舞台に並びますものね。
福井 確かにそうですね。
小川 取材で帝国劇場の一般には入れない場所を見せていただき、舞台にも立たせていただいたのですが、何の役でもない生身の人間が舞台に立つというのはとても異常なことで、居心地が悪かったことを覚えています。
舞台上でどこで何をやるかというのはきっちり決まっているんでしょうか。ここでこの台詞を言う、ここでこういう動作をするとか。
福井 決まっている部分と自由に動ける部分があります。照明の効果を生かすために、絶対に守らなきゃいけない場所もある。たとえば「レ・ミゼラブル」の「ワン・デイ・モア」の歌い始めの場所は必ず守りますが、自由なところもあります。
小川 「レ・ミゼラブル」のプロローグに出てくる「バルジャンの独白」は何分ぐらいあるんですか。
福井 3分ぐらいでしょうか。
小川 ほんの短い時間ですが、その間に劇的なことが彼の内部で起こっています。独白を歌い終え、身分証を破って、ジャン・バルジャンがいなくなってようやく「レ・ミゼラブル」というタイトルが出るのですが、えっ、今から始まるの? もう半分終わったんじゃないかといつも思います。
福井 バルジャン役者はみんな言うのですが、「バルジャンの独白」で大体半分終わる、プロローグはそれぐらいの密度です。
小川 3分間で人間があそこまで生まれ変わる姿を、不自然じゃなく観客に納得させるのは歌だから成り立つというのはありますよね。
福井 「レ・ミゼラブル」は音楽が全部導いてくれる作品です。音楽の力って本当に強いです。「レミゼ」は最初は自分で考えてきたものを見せ、ディスカッションしてつくり上げていきました。何度も繰り返し稽古して、演出家の指示も細かくある。バルジャンがどこで決意するのかは、役者によってアクションが違ったりするんですよ。それぞれの役者のいい部分が採用されています。
小川 ダブルやトリプルキャストの場合、違っていてもいいんですか。
福井 アイデアは汲んでくれるので、人によって違う部分もあります。
小川 私は福井さんのバルジャンが好きで、ずっと福井さんばかりを見ていたんですけど、あまりにも好き過ぎたために、ほかの人と比べてみたいという気持ちが出て、2021年には吉原光夫さんと佐藤隆紀さんのも観たんです。そして福井さんにまた返るという、完全に東宝の罠にはまっています。
福井 返ってきていただいて嬉しいです。
小川 お三方のを拝見して、福井さんのジャン・バルジャンが一番父性が強いと思いました。コゼットに対してお父さん的な愛の深さが前面に出ている。バルジャンはコゼットと出会っていなかったらもっと堕落していたかもしれない。
福井 まずは司教との出会いがあり、コゼットという自分よりも大切なものを得て、彼の人生は変わったんじゃないでしょうか。
小川 自分より大切な人と出会う人生でありたいですよね。人ではなく犬でも植物でもいいのかもしれないけれど、自分が一番大事、自分のことが一番心配という人生はいつか行き詰まって苦しくなってしまう。私は自分のお葬式の出棺のときには福井さんが歌う「彼を帰して」を流してもらいたいと夫に言ってあるのですが、「彼を帰して」の歌詞はまさに「てなもんや三文オペラ」の「ただいま」に繫がりますよね。死ぬのは老いた自分であって、若い子は「ただいま」と家に帰らなくちゃいけない。「彼を帰して」は神様との対話です。
福井 神に対する怒りと演出家は言っていました。懇願ではなくそれぐらい強いものでいいと。
小川 神様の前にひざまずいて「どうかお願いします」というよりは、なぜこんな若者たちが死ななくてはならないのかと神を問い詰めているんでしょうか。
福井 2013年、15年上演時はどちらかというと懇願だったんですけれど、21年の演出家の要求はより神と対峙する方向に変わってきて、そう演じるようになりました。でも、難しいんです。美しいメロディーなのに、怒りを出すことでそれが崩れたりすることもあって。
小川 キーも非常に高いですよね。
福井 はい。ファルセットも使いますし、技術を必要とする曲で、ほぼ満足することはないです。
小川 何度拝見しても毎回、今日が史上最高だと、完璧に聴こえるのですけれど。
「レ・ミゼラブル」のような3時間にもなる複雑なお芝居をやっていて、案外ハプニングって起こらないものですね。観客にばれるような取り返しがつかない失敗は。
福井 歌詞を間違えるくらいで今まで舞台が止まるようなことはないです。
小川 それで短編集の中の「ダブルフォルトの予言」という作品では、帝国劇場の中にはきっと失敗を予言するような妖精みたいな人がいて劇場を守っているんじゃないかなという空想をめぐらせたのですが。
福井 すごい共感できました。劇場には必ず舞台の神様がいると思っています。
小川 劇場裏には神棚がありますよね。
福井 あります。毎回、本当に、小説に書いてあるように、怖いんです、舞台に立つというのは。しかも帝劇のセンターに立つのは、何回やっても怖くて不安で、どこかで神頼みじゃないですけれど、毎公演祈りながら立っています。そういう意味でもすごく勇気を頂ける小説でした。舞台を好きな人が読んだら、たくさん発見があると思います。劇場の裏を知ることができる。
小川 何の仕事をしているのかよく分からない人がうろうろしているイメージがあるんです。
福井 どの方もいなくてはならないのですが、一見こんなに要るのかなというぐらいの人数がかかわっています。
小川 その中に一人ぐらい妖精が混じっていたって誰も気づかない。誰の目にも映らない人がいてもいいんじゃないか。そして広い劇場の中に人が住んでいたっておかしくないなという気持ちになって書きました。
福井 本当に多くの方に支えられています。それにしても小川さんの発想はやはりすごいですね。
小川 これまでも病院、博物館、標本室、島など閉じられた場所を舞台にして書くことが多かったのですが、劇場はまさに閉じられた空間です。劇場のことを箱と言いますよね。現実から切り取られた特別な空間で、小説になりそうなネタがいっぱい詰まっている場所でいくらでも書くことが浮かんできました。
でも特にコロナ禍になってなおさらですけど、一回の公演が始まって、無事に幕が下りるというのは奇跡的なことなんだなと思わされます。
福井 本当にそれは実感しています。
小川 役者さんの技術や頑張りだけではどうしようもない。何者かの力が働いているように思えます。
福井 お客様を入れて舞台をやれるというのは奇跡ですね。

「すばる」2022年10月号転載
【後編へ続く】
関連書籍
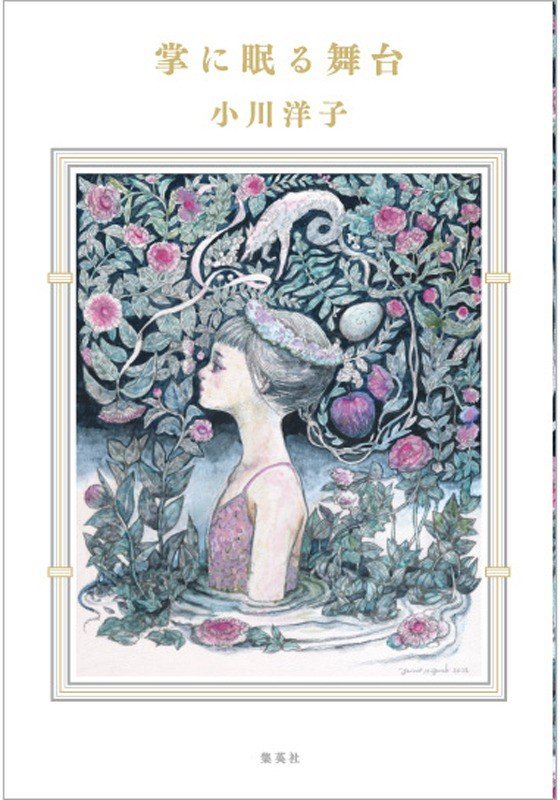
小川 洋子
集英社
定価:本体1,650円+税
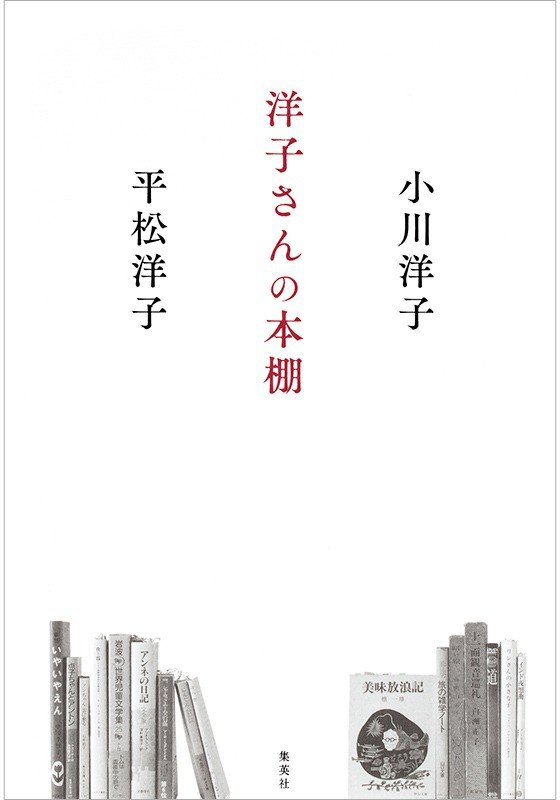
小川 洋子 平松洋子
集英社
定価:本体1,500円+税

























