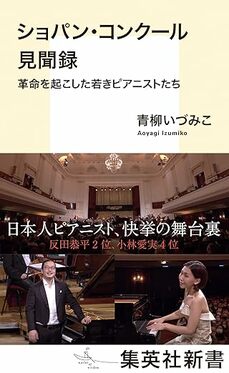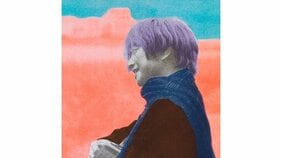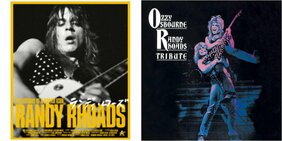演奏順にファイナリスト11名の演奏を振り返る
以下は、ファイナリスト11名の出場順レビューだ。
①リ・ティエンヨウ(Li Tianyou)【中国】
本選は、第3次予選では初日の最後に弾いたリ・ティエンヨウ から開始。もし第1予選の組み合わせ通りなら、彼は7番目で2日目の3番手になるはずだった。これはかなり大きな違いだ。楽器はスタインウェイ。堅実なテクニックと知的なアプローチでファイナリストとなり、2次予選の『英雄ポロネーズ』によりポロネーズ賞も獲得しているティエンヨウ。
リズム感は抜群だが、本選の『幻想ポロネーズ』ではもう少し「歌」が欲しかった。私が聴いた3階席バルコニー(審査員席の真上)では、中音部域の音の伸びが今ひとつだったので、そのせいもあるかもしれない。協奏曲は1番。旋律が高音部域に移ることもあり、よく鳴っていた。テーマの歌い方は初々しく、オケとの対話も良い。とりわけ3楽章は、達者な技巧を駆使して溌剌と演奏された。
②エリック・ルー(Eric Lu)【アメリカ】
本来は第3次予選で2日目の2番目に演奏予定だったが、体調不良で最終日の最後にまわったため、セミファイナルの翌々日の午前中に演奏することになった。楽器はファツィオリ。『幻想ポロネーズ』の際には、見慣れたピアノ椅子ではなく、赤いパイプ椅子に座っていた。レパートリーに合わせて椅子を変えるとのことで、しばしば背もたれに身体を預けて弾いていた。
2015年のコンクールで代名詞になった「夢見るように弾く」イメージ通り、遅めのテンポを取り、内省的なアプローチで沈みがち。もう少しマインドが開いても良いのではないかと思った。『協奏曲第2番』では、ファツィオリの椅子に戻して演奏。ピュアな抒情が曲想に良く合っている。2楽章のテーマは煌めく音で密やかに歌われ、3楽章のマズルカ風の主題の歌い方が素晴らしかった。快速のパッセージはキレが良く、左手はスタッカートで軽やかにリズムを刻む。ラストはキラキラ光るスケールで締めくくった。
③リュー・ティエンヤオ(Tianyao Lyu)【中国】
リュー・ティエンヤオ もファツィオリを使用。前に演奏したエリック・ルーに比べて、音がくすんで聞こえる。『幻想ポロネーズ』の序奏は転調に沿って徐々に花開くように設計されていた。コラールはもう少し重量感が欲しく、コーダはミスタッチが目立ったが、息の長い音楽性は天性のものだろう。協奏曲賞を得た『協奏曲第1番』は楽器も良く鳴り、見事な演奏だった。第1楽章、第1主題の歌い方は初々しく、音もよく伸びる。表情豊かでオケとの対話も良い。3楽章はキラキラ輝く音で、リズムに乗り、快速のスピードでも乱れず、元気いっぱいに弾き切った。
④ヴィンセント・オン(Vincent Ong)【マレーシア】
ヴィンセント・オンはシゲル・カワイを使用。『幻想ポロネーズ』は素晴らしい演奏だった。重量感のある出だし。ポロネーズ部分も上声がよく歌い、対旋律を強調し、左手は雄弁。コラール部分も深々と。コーダでは、左手のオクターブが見事に入り右手は自在に歌う。『協奏曲第1番』も間の取り方が巧みで、適度に空気を入れつつ、色濃く歌い上げる。
指揮者の感覚で自分を操りながら弾いている感じで、2楽章は装飾を加えながら切々と歌い上げていく。3楽章のテーマの弾き方もさまざまに変化させる。拍の付け方が本当に上手で、速いパッセージでも濃淡をつける。もっと上の順位に行っても良いと思うピアニストだった。
⑤進藤実優【日本】
進藤実優はスタインウェイを使用。全身全霊を傾けるスタイルで全てが連動し、沈黙の雄弁さも含めてひとつの物語を紡いでいくような演奏。『幻想ポロネーズ』の冒頭から、深いバスの響きが伝わってきた。非常に集中力が高く、たっぷりとる間合いも含めて、晩年の精神性を余すところなく表現していた。遅いテンポで息長くしみじみと歌われたコラール。ひたひたと階段を登り、迫力のあるオクターブと右手の和音で歌い上げるラストも素晴らしかった。
『協奏曲第1番』も、オーケストラを超えて煌めく音がよく伝わってきた。第1楽章のイントロから激しく感情移入し、第1主題は訴えるような音で、第2主題も、ゆったりしたテンポで切々と歌う。速いパッセージでもリズムに乗りながら歌謡性を失わない。しっとりと内省的な2楽章、身体全体で躍動する3楽章と渾身の演奏。独特の跳ね上げるような奏法でややミスが多くなったのが惜しまれる。
⑥ワン・ズートン(Zitong Wang)【中国】
ワン・ズートン は、シゲル・カワイを活かした柔らかな音色と語りかけるような歌い方で『幻想ポロネーズ』をしみじみと奏でたが、準備不足からか、左手にメモリーミスが散見された。『協奏曲第1番』は息の長い音楽とひとつひとつが微笑んでいるような音で客席を惹きつけた。オーケストラとも良く息が合っている。第2楽章はたっぷり間を取り、青春の匂いたつような抒情を歌いあげる。第3楽章は一転してキレの良いタッチと弾むリズムでチャーミングに奏でられた。ずっと白いジャケットで通したズートンのソナタ賞(3次予選での第2番の演奏に対して)を心から祝いたい。
⑦ウィリアム・ヤン(William Yang)【アメリカ】
本選は3階席バルコニーで聴いたこともあり、ウィリアム・ヤンの演奏については評価が一転した。予選ラウンドでは音楽作りの方向が見えづらかったが、ファイナルで聴く『幻想ポロネーズ』は、イントロから、優れた構成力が伝わってきた。全体を見渡した上で、達者なテクニックを駆使してさまざまな要素を操り、決して冗長にならないところが良い。
『協奏曲第2番』は非常に軽く、非常に繊細なタッチで弾かれたが、どんなに音量を絞ってもオケに埋もれないのが凄い。使用楽器はスタインウェイなのだが、まるでフォルテピアノで聴いているようだった。
⑧ピオトル・アレクセヴィチ(Piotr Alexewicz)【ポーランド】
ピオトル・アレクセヴィチはシゲル・カワイを使用。『幻想ポロネーズ』は旋律とリズム要素を分けて立体的にメリハリをつけて弾いていた。『協奏曲第2番』は、ソフトな音で端正に演奏された。第1楽章の第1主題は切々と訴えるように、展開部も繊細な音でピアノを美しく歌わせていた。2楽章も滑らかなタッチで歌い上げる。ヴァリアントの途中でフェードアウトするのがとても綺麗だった。3楽章は音に芯があり、マズルカのリズムを的確に弾ませていた。
⑨ケヴィン・チェン(Kevin Chen)【カナダ】
ケヴィン・チェンはスタインウェイを使用。予選ラウンドを通じて卓越した技巧と優れた構築性で勝ち進んできたピアニスト。『幻想ポロネーズ』も主情に傾きがちな弾き手が多い中、バスや内声の動きを強調し、立体的な音楽作り。『協奏曲第1番』では、全ての音を芯に当てて粒を揃え、技巧的な部分でもあまりテンポを変えることなく、不動の演奏。音は明るく綺麗だが、やや堅苦しい印象がある。もう少しシーンごとに色が変わっても良いかなと思った。
⑩ダヴィド・フリクリ(David Khrikuli)【ジョージア】
ダヴィド・フリクリはスタインウェイを使用。『幻想ポロネーズ』は、座っていきなり弾き始めたので少しびっくりした。序奏は転調ごとに色彩を変え、魅力的だったが、ポロネーズ部分はテンポが速めで、期待されたような円熟味はあまり感じられなかった。 『協奏曲第2番』の呈示部も同じような印象を持ったが、展開部あたりから音が訴える力を持ち始め、陰影をつけて切々と歌う再現部は美しかった。2楽章は蕩けるように美しく、3楽章も軽やかで表情豊かに演奏されたが、もう少しヴイルトゥオーゾ的な要素も欲しかった。
⑪桑原志織【日本】
桑原志織もスタインウェイ。素晴らしいステージで、コンクールであることを忘れさせた。『幻想ポロネーズ』は充実した響きで、各パートを適切に配置し、ドラマティック。手が違うところに飛んで一瞬ひやっとする場面もあったが持ち直し、コーダは徐々に盛り上げて輝かしく終える。『協奏曲第1番』も良く伸びる音でナラティブな演奏。
フレージングが細やかで包容力がある。速いパッセージでも全ての音が煌めいている。2楽章もたっぷり間をとって、オペラ歌手のように自在に歌われた。オケを装飾する部分もルバートをきかせて夢のよう。3楽章はエレガントで軽やかに弾かれた。少し集中力を欠く場面もあったが見事に弾ききり、この日一番の歓声を浴びた。この時点では3位以内の入賞を確信していたので、結果は少し残念に思われた。
文中敬称略
※ショパン国際ピアノコンクールに出場している日本人以外のピアニストの名前はカナ表記の後にカッコ()で欧文を記載。本大会の演奏はYouTube:Chopin Institute( @chopininstitute)で視聴が可能だ。