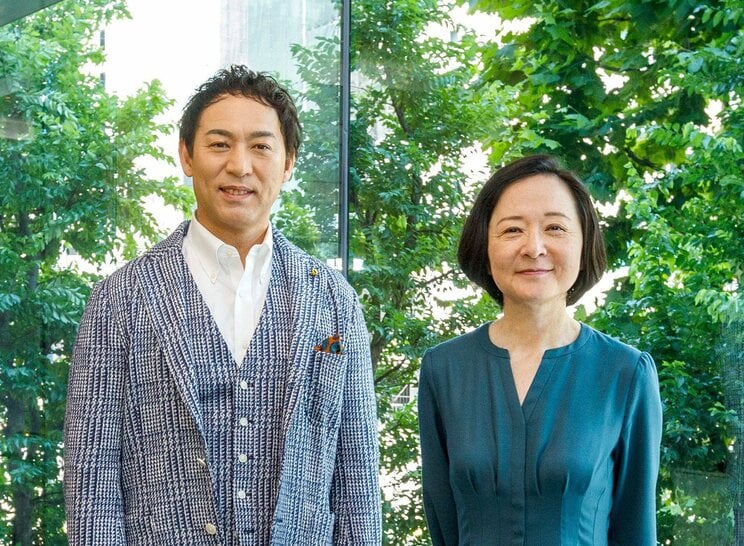小川洋子さんの最新短編集 『掌に眠る舞台』が刊行される。この作品集には演じる、 観る、観られるーー特別な関係が生まれる「舞台」にまつわる8編の物語が収められている。小川さんが足しげく劇場に通うことになったのはある歌声に魅せられたから。その声の主であるミュージカル俳優・福井晶一さんとの念願の対談が実現した。
構成/すばる編集部 撮影/中野義樹 (2022・6・27 東京にて)
歌を仕事にすることを選んで
小川 ジャン・バルジャンを演じる福井さんはたった一人舞台に立ち、それを帝劇ならば2000人の人が見ています。普通の人間は一生のうちに一度としてできない経験をされているんですから、やはり特別な役目を、宿命を背負って生まれてこられたんですよ。
福井 本当に命縮みそうですけどね、一回一回。
小川 でも、北海道の野球少年がなぜミュージカル俳優になられたんですか。
福井 姉が舞台が好きだったんです。僕も子どものときから歌うことは好きで、歌を仕事にできたらいいなと思っていました。あと、野球も同じくらい好きで、小学校の卒業文集に将来の夢を歌手かプロ野球選手と書いたぐらいです。高校までは甲子園目指して野球をしていました。バンドブームがあったりして、ギターも買ったりはしましたが。高校球児の夏が終わってすぐミュージカルに興味を持ち、劇団四季の「CATS」札幌公演に姉に観に行かないと誘われて、あっ、これならできるかもしれないと勘違いしちゃったんです(笑)。
小川 できたじゃありませんか(笑)。
福井 「CATS」を観たその衝撃で、内容がどうとかというよりも、華やかなステージで自分も歌いたい、歌の好きな自分なら仕事にできるんじゃないかなと、そのとき東京に行くと決めたんです。ただ、実は野球で就職が決まっていました。なので1年は仕事をしながら野球をしてお金を貯めて、翌年ミュージカルの専門学校に入りました。
小川 劇団四季は一発で合格されたんですよね。すばらしい。
福井 男性の受験者が少なくラッキーだったと思います。当時、志願者は圧倒的に女性が多かったんです。舞台芸術学院の1期先輩に濱田めぐみさんがいるんですけど、ハマちゃんは1度めは落ちているので。
小川 えーっ。
福井 学院の中でもずば抜けてうまかったあのハマちゃんがと驚きました。
小川 そこにも運というか、巡り合わせというか、自分の力以外の何かがありますね。
福井 本当は音楽座を志望していたのですが、たまたま劇団四季のオーディションが先にあり、合格の通知を受けたのも運命なんだろうなと。
小川 「CATS」へのご出演は2000回だそうですね。
福井 2000回以上、三つの役で出演しました。
小川 18歳の少年の時観た舞台に自分が立つなんて。感慨深いものがおありだったんじゃないですか。
福井 無我夢中でした。札幌のJRシアターというところで立たせていただいたんですが、初参加でタンブルブルータスとマンカストラップという二つの役を同時に覚えて、タンブルブルータスで6週間出た後にすぐにマンカストラップも演じ、それは本当に大変でした。
小川 想像するだけですけれど、浅利慶太さんのご指導は厳しかったですか。
福井 劇団四季の稽古場には「一音落とす者は去れ」という有名な格言が貼ってあって、本当に一音聴こえなかっただけで去っていった人もいます。僕もマンカストラップを演じている時、浅利先生が札幌までいらして、全然駄目だと、次の日に東京に帰されて交代ということがありました。
小川 残酷な世界ですね。
福井 そこから2年ぐらいまたアンサンブルの時代があり、再びマンカストラップをやる機会があって、そこで何とか先生に認めていただきました。
小川 それにしても2000回以上とは。飽きないものですか。
福井 よく訊かれるのですが、僕はいつも新鮮にやらせてもらっていました。「CATS」の稽古に入るときに先輩から、「舞台に立つ2時間半、とにかくあなたは猫で生きなさい」と言われたのが強く残っていて、毎回その言葉を思い浮かべながらやっていたので、猫という人間ではないものを演じることに喜びと、楽しさがありました。もちろん体が疲れていたりするときは大変でしたけど、それ以上にやりがいのある役でした。僕自身が公演委員長という立場を引き受けてからは、舞台を引っ張って背中を見せなきゃいけないという気持ちもあったので、慣れてとかだれてとかということはなかったと自分では思っています。
小川 猫、つまり、さっきも言いましたけど、舞台上ではこの世のものじゃない何かになるという典型的なパターンですよね。人間でさえないものになる。
福井 メイクをして、しっぽつけると、マジックがかかるんです。
小川 四季を辞める決断というのは何かきっかけがあったんですか。
福井 入団1年めにアンサンブルで出た作品「美女と野獣」の野獣役をやりたいという一つの目標が叶ったからですね。外の世界でもやってみたいという思いはその数年前からあって、年齢的にもチャレンジするなら今じゃないかと。すばらしい役者さんは劇団四季以外にもたくさんいらっしゃるので、そういう方と一緒にお芝居してみたいとも思いました。
小川 それで「レ・ミゼラブル」のオーディションをジャベール役でお受けになったんですよね。
福井 はい。自分の中ではジャベールしか選択肢はなかったんですけど、友人に薦められて両方出してみたら、新しいバルジャンをつくりたい制作と僕のタイミングがうまくかみ合ったんです。ただ躓きましたけど……。
小川 運命を恨まれたんじゃないですか。
福井 ジャン・バルジャンが決まって、昔から応援してくれてた方、家族、友人たちとみんな本当に喜んでくれた中で稽古中に大怪我をしてしまったので、どん底でした。
小川 あれも必要な経験だったのかなと思えるときが来ましたか。
福井 経験しなくてもいいものではありましたが、バルジャンを演じる上でその思いというのは助けになりました。
小川 アキレス腱が切れた絶望の感情の中にジャン・バルジャンを演じるのに必要な何かが潜んでいたと。
福井 あくまで今思えばですけれど。俳優としてそこまで順調に行き過ぎていたんじゃないかなと思うし、挫折を味わったことで演じる一つのヒントを得たと思います。
怪我が治っていよいよデビューの前に、オーケストラのみなさんに付き合っていただいて公演後の帝劇で「独白」を一人で歌ったのを見ていてくれた仲間がいるんです。彼らは今でも「あのときの福井さんには取りつかれたものがあって忘れられない」と言ってくれる。僕自身は必死だっただけですが、なにか言い知れぬ感情が出ていたんだろうなと。
小川 舞台を観ている私たちは、歌の歌詞の意味を理解して、それを解釈して感動しているわけではなく、人間の肉体が発している、言葉にならない何物かを受け取って、意味も分からず感動しているんです。それを発するのが俳優さんの大事なお仕事です。だからこそ人生経験は何一つ無駄にはならないと思います。身に起きた良いことも悪いこともどういうふうに解釈するかということで生まれてくるものがあるでしょうから。
福井 若い頃は僕も勉強不足だったので、自分の感覚だけでやっているところがあったんですけど、劇団四季が重きを置くのは言葉。言葉、言葉、言葉とよく浅利先生はおっしゃって、言葉が一音でも届かなかったら作品は駄目になる、感情の前に言葉だと。物語を一言一句ちゃんと伝えれば感動が伝わると教えられてきた。それに劇団は同じ仲間で長い時間稽古を積み上げられる環境でしたが、辞めたあとの公演は1か月ぐらいの稽古で本番がくる。自分自身というものをもっとアピールしなきゃいけないし、自分が作品で求められているものが何なのかを考えるようにもなりました。どういうふうに演じたいかとか、この台詞をどうしゃべりたいか、自分から発する主体性をしっかりと持たなければと。役の捉え方は年々変わってきています。
小川 まず台本が手元に届くと、どういう読み方をされるんですか。
福井 邪魔されないようにゆっくり読みます。最初から台詞にして読むと、全体の流れ、ストーリーが入ってきにくい。自分の台詞ばかりを追う癖があるので、そうならないように、落ち着いた静かなところでまず読むようにしています。そこから徐々にワンシーン、ワンシーンの中で何が求められているかとか、自分の役がこのシーンでどういう役割なのかというのを分析していく。あとは、想像力じゃないですけど、台本に書かれていない部分の役の背景、たとえば具体的な年齢が書かれていないこともあるので、それを自分で勝手に設定してという形です。
小川 この間必要があって『ハムレット』の脚本を読んだのですが、登場人物たちが死をさまざまに画策するのに、誰一人計画していた死に方はできない。演出の仕方次第で最後は喜劇にもなるななんて思いました。「ユニコーンを握らせる」という短編でも取り上げた『ガラスの動物園』も読んでいたときはローラという女の子の孤独が胸にしみたのですが、母のアマンダ役を麻実れいさんが、ローラを倉科カナさんがされた公演を観たら、むしろ母の狂気のほうがわーっと迫ってきて、脚本読んで観に行くのも面白いなと思いました。
福井 『密やかな結晶』が舞台化されたとき、お書きになったものを観る気分はいかがでしたか。
小川 小説の中におじいさんという人が出てくるんです。名前はなくて、おじいさんとしか呼ばれておらず、主人公の「わたし」に心の底から仕えている。「わたし」は自分より大事な人で、この人のためなら死んでもいいという気持ちで尽くしているおじいさんの役を20代の村上虹郎さんがなさったんです。今回福井さんがジェニーを演じられたことにつながる、一種の鄭さん独特のマジックですよね。
小説の中には、おじいさんが「わたし」に対して持っている愛情みたいなものは直接的には書かれていないのですが、鄭さんはそれを村上虹郎さんに歌わせたんです、「ソロモンソング」のように。彼が一人で買物かごを持って歌うシーンがあって、それは原作にないオリジナルで、作家が書かなかったことを作家が思いもつかない方法で表現された。それを楽しめるのは作家一人なので、特権だなとうれしかったですね。