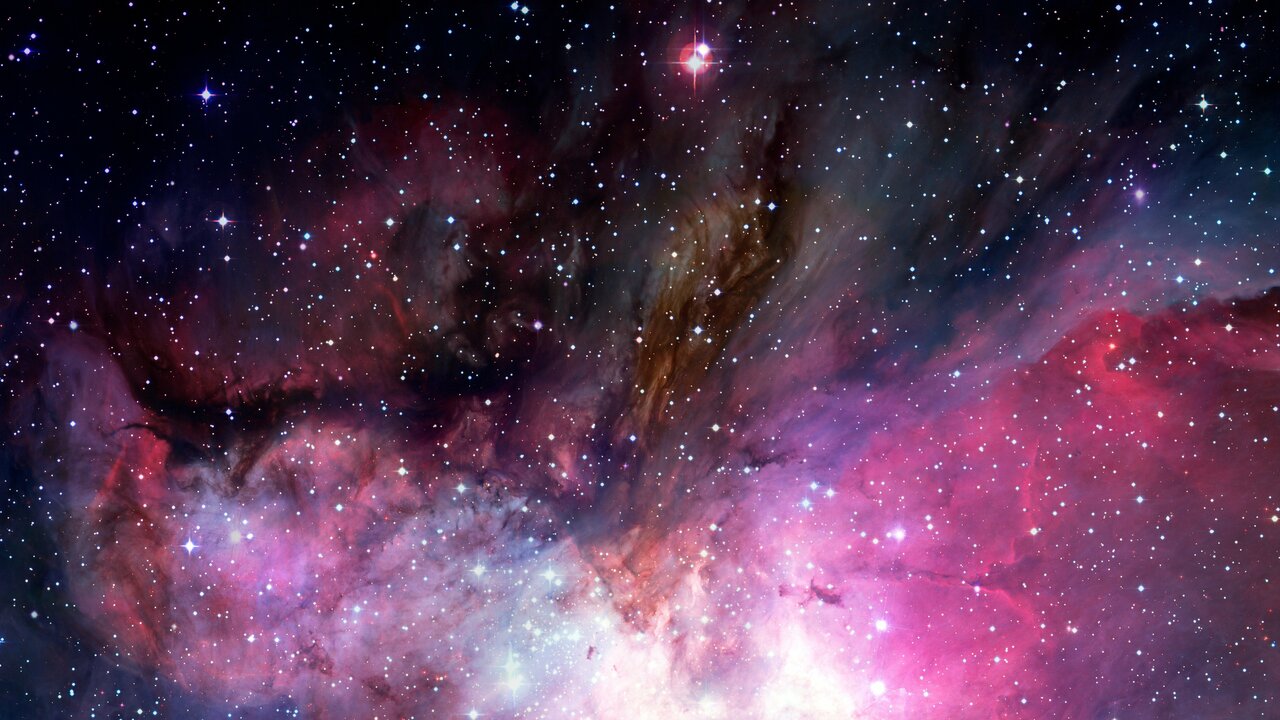音楽は祈りです。あなたはまだ足りないよ
冬木氏は1935年、満州生まれ。広大な大陸で病院の屋上で行われたレコードコンサートや、父親の部屋から聞こえてくるワーグナーに深く心を動かされながら育った。
しかし、やがて日本は敗戦。冬木氏の家族も大変に苦労しながら日本に戻り、広島に住むことになる。現代であれば、ネットでどんな音楽でも無尽蔵に接することができるが、当時はそうはいかない。だがそれでも音楽との出会いはあった。
こうして入学した八重高校には音楽関連の部活動はありませんでしたが、ある日音楽室からピアノの音が聞こえてきました。行ってみると、大きな男がピアノを弾いているのです。一学年上の児玉君という、父親が精神科医をしている先輩でした。近寄ると「ああ、蒔田ってきみ?」と言われました。転校生に音楽ができる奴がいる、と噂になっていたようでした。(第一章 私の音楽の源泉 ~満州・上海と広島時代)
蒔田とは冬木氏の本名。戦後の厳しい時代でも音楽を愛する人はいた。冬木氏は、ある時は「音楽の勉強がしたいんです」と頼んだ先生に「お前そんなことで、家族を食わせていけると思ってんのか!」と怒られながら(その先生は私財で楽器を買い生徒に渡していたらしい)、やがて広島にちょうど創立されたエリザベト音楽短期大学に入学する。
医師である父は、実は冬木氏が音楽を学ぶことに大反対で、そのために父子は口もきかない時期があったほどだった。
しかし卒業を前にしたある日、学校から帰ってくると机の上に何かが置いてありました。何だろうと思って見てみると、それは入学願書でした。ちょうど私の高校卒業のタイミングで、広島にエリザベト音楽短期大学が創立・開校されることを知った父は、その願書を取り寄せてくれていたのです。(第一章 私の音楽の源泉 ~満州・上海と広島時代)
冬木氏は進学した学校でクラシック音楽、特にキリスト教音楽を学んだ。エリザベト音楽短期大学は、イエズス会士のエルネスト・ゴーセンス神父が「原子爆弾の惨禍を被った広島の地で文化の灯火を」と考えて始めた音楽教室がもとになっている
後に学長になったゴーセンス神父がよく冬木氏に語った言葉が「まだ足りない。音楽は祈りです。あなたはまだ足りないよ」だった。
この学校でラテン語の意味まで吸収しつつ、貴重な経験を得た冬木氏は上京。ラジオ東京(後のTBS)に就職し、そこで音響効果を担当。そしてさらに国立音大で学ぶ。
やがて作曲も手掛けるようになって独立し、時代劇、ホームドラマなどさまざまな分野で腕をふるうようになった。時代は1960年代、高度成長の季節だった。
一九六〇年代当時、テレビの現場ではハードの進歩が早くどんどん新しいものが出てきて、音楽でも録音技術が急速に進化していました。「表現の技術と思想の進化」と「ハードの発展」が同時に起こり、ハードとソフトの両方が大きく羽ばたいた時期にそこに居合わせたのは幸運でした。(第二章 東京へ ~ラジオ東京勤務)
社会も変わり、自分も成長する。可能性の時代に居合わせた「幸運」をもっとも如実に感じた仕事が、ある特撮番組だったと冬木氏は語る。それが『ウルトラセブン』だ。