事故を未然に防ぐことが最大のミッション

新型コロナウイルスの影響で客足が途絶えていたビーチは今年、徐々に活気を取り戻した。一方で、悲しい水難事故のニュースも相次いだ。
日本全国にある海水浴場の数は約1200。必ず安全監視員を置かなければならない条例があるものの、日本ライフセービング協会が発行する資格を持つ、認定ライフセーバーがいる海水浴場は、わずか200ほど(https://ls.jla-lifesaving.or.jp/accident-prevention/safety-beach/)。そのほかの場所では、資格を持たない地元の有志などが監視をしている。ライフセーバー人口の不足など、海の安全を守る基盤が十分整っていないのが現状だ。
では、どうすれば水難事故を防げるのか。現役で活動するライフセーバーたちは、「自分の命を自分で守ることが一番」だと語る。
「海の危険性を理解し、その日のコンディションを見た上で正しい遊び方を判断できれば、極論、事故は起こらないんです。もちろん、誰もが高い安全知識を持っているわけではないので、僕たちからお声がけして、安全に遊んでもらえる方法や場所を伝えています」(上野)
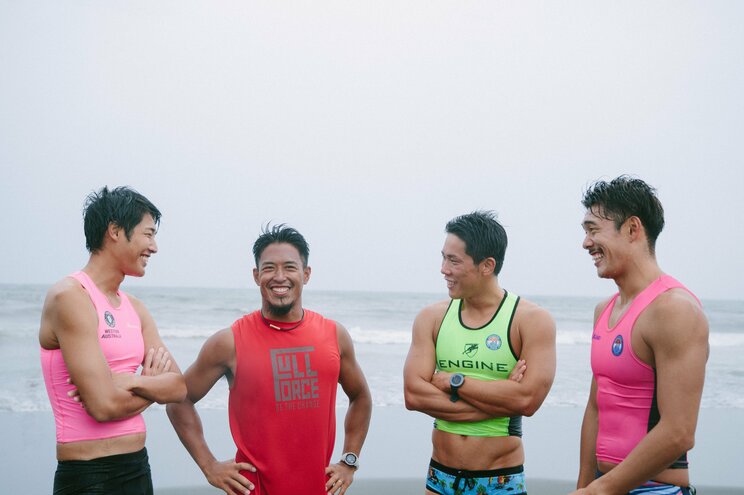
現場でさまざまなセーフティネットを張ってはいるが、もしも疑問や不安があったら、気軽に「今日はどうすればいい?」と話しかけてもらいたいともいう。
「僕たちは救助することが仕事だと思われていますが、溺れるのを待っているわけではありません。事故を未然に防ぐことが最大のミッション。もちろん、事故が起きたときに救うためのトレーニングは積んでいますが、日頃から、“どうすれば事故が起きないか”とチームで話し合い、予防策を練っています」(園田)
海のコンディションが大きく変わる要因は、風と波。特に離岸流は、自分で岸に戻ろうとしてもコントロールできないため、パニックになってしまうことが多い。
「ライフセーバーは“うるさい監視員”みたいに思われることも多いのですが、僕たちの近くで遊んでくれることも、安全性を高めるために大切なこと。人が少ない場所で遊びたい方もいると思いますが、目が届かない場所では何かあったときにすぐに駆けつけることができません。早朝や夜など、監視していない時間に事故が起こることも多いので、時間と場所を守っていただきたいです」(西山)
日本の海水浴場では、飲酒による事故も多い。
「飲酒して海に入ることを許されている国って、実はすごく少ないんです。諸外国では、ビーチでの飲酒を禁止しているところが多い。それだけ、飲酒は危険だということも覚えておいてください」(西山)
















