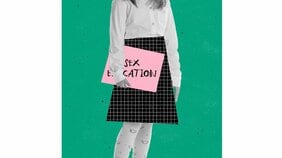「昔の氏名でも検索を」データベースの厳格運用で、再任用防止
「大分県教育委員会において適切な確認をしていなかったということは遺憾であり、指導を行った。教育職員等による児童生徒への性暴力等から子どもを守り抜くために、しっかりと取り組みたい」
永岡桂子文科相は3月24日の会見で、女子中学生の体を触ったとして有罪判決を受け、執行猶予中の男性が、大分県の小学校で非常勤講師として勤務していた事案に触れ、再発防止を誓った。こうした子どもへの「わいせつ歴」がある人物を再び教育現場に戻さないよう、文科省は対策を強化している。
その柱の一つが、4月から運用を始めるデータベースだ。ここには、子どもへのわいせつ行為で教員免許を失効した元教員の氏名や失効理由などが、過去40年分にわたって登録される。
文科省が、データベースの運用に先立ち、3月に各都道府県教委などに通知した文書では、教育委員会や私立学校が常勤・非常勤に関わらず教員を採用する際には、このデータベースで氏名を検索することを義務づけた。
教員免許を失効した元教員が意図的に改名し、検索に引っかからないようにするケースも想定されることから、現在の氏名だけでなく、大学の卒業証書の氏名でも検索するよう求める徹底ぶりだ。
「データベースに載っていると判明した人物を教育委員会が採用することは、まずないでしょう。データベースに載った人物の再任用は、かなりの確率で防ぐことができます」(文科省官僚)