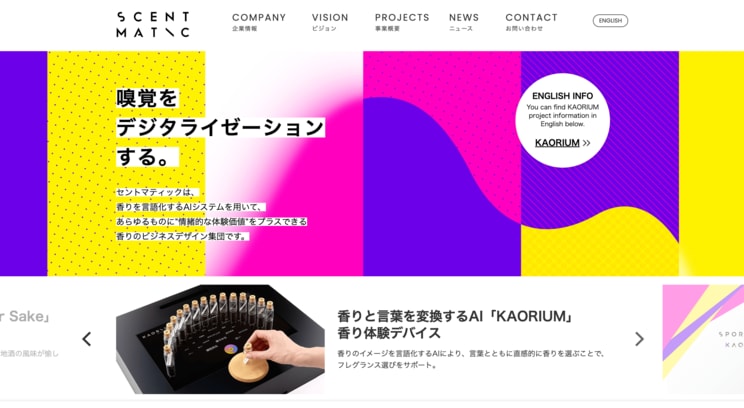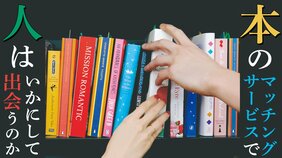「嗅覚×テクノロジー」の注目サービス
視覚、聴覚、味覚、触覚、嗅覚。人間の生活を支えるこれらの感覚を「五感」と呼ぶ。視覚や聴覚に関しては古くから研究がなされ、さまざまなプロダクトやサービスが生み出されてきた。
一方、五感の中でもっとも謎めいていたのが嗅覚、すなわち「ニオイを感じる」感覚である。我々にとって極めて重要な機能であるにも関わらず、そのメカニズムは長く解明されなかった。ニオイを感じる器官である嗅覚受容体の存在が発見され、ノーベル賞が授与されたのは21世紀に入ってからというから驚きだ。
そんな嗅覚とテクノロジーを組み合わせ、新しい体験を提供するサービス「KAORIUM」(カオリウム)が注目を集めている。
KAORIUMとは、いったいどんなサービスなのか。開発・提供を手掛けるSCENTMATIC(セントマティック)株式会社の代表取締役・栗栖俊治さんに、詳しい話を聞いた。