なぜ絵日記が夏休みの宿題として出るのか?
――7月28日に「夏休み絵日記ドリル」(講談社)を出版されましたが、あきやま先生は夏休みの絵日記の宿題はなぜ出されるとお考えですか。
子どもたちの現時点の表現力を確認する指標として宿題に出されるのではないでしょうか。と同時に、それらを伸ばすトレーニングの働きもあるのだと思います。
絵日記の文章は、「いつ」「どこで」「だれと」「何をして」「どう思った」という、作文として最も基本的な要素で構成されますが、これを夏休み中に毎日トレーニングとして積み重ねていくことで、読書感想文や国語科の作文などを書く力をつけていくのだと思います。
絵に関しても同様ですね。毎日の1シーンを描くことで、絵を描く力を着実につけていくことができます。絵日記の絵がすらすらと描けるようになれば、図画工作の絵画なども苦労せずに描けるようになると思いますよ。
絵が苦手なのはなぜ? 上手く描くコツとは
――作文はなんとか書けても、絵が上手く描けずに苦労するという子も多いようです。
絵が上手く描けない理由は、単純に描き方を知らないからです。ポイントを押さえれば、人や動物、花などはすぐに描けるようになります。
例えば、動物園に行ったことをライオンの絵とともに表したいとしましょう。多くの人はライオンを描きたいと思うと、ライオンの「シルエット」だけが頭に浮かんでいる状態、つまり、ひとかたまりの形として捉えています。細かなディテールはぼんやりという場合が多いです。
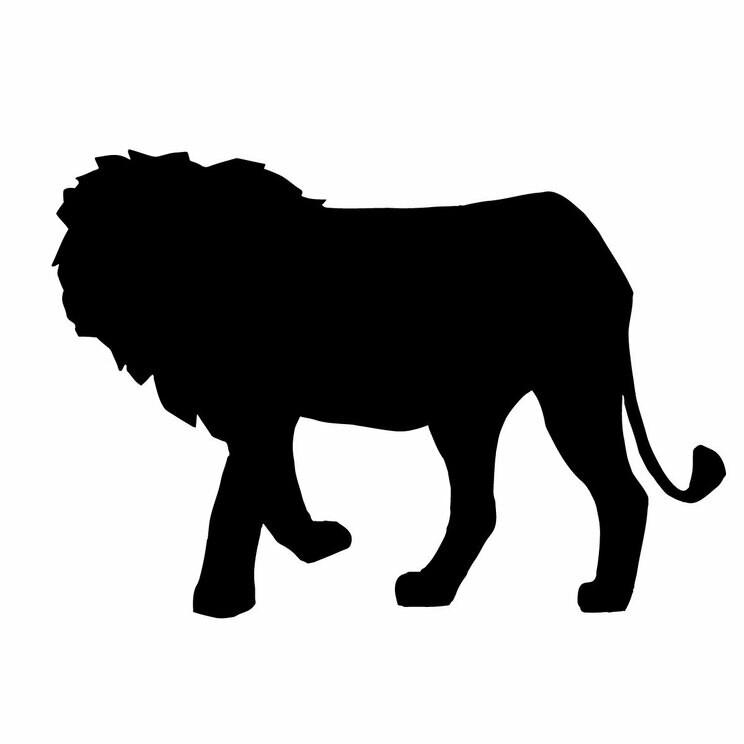
シルエットだけをイメージしてしまうから、足はどこから生えているのか、耳はどんな形なのかなどが上手く表現できないんですね。生き物は主に頭・胴・足で成り立っています。これらをどう組み合わせると描きたいものに近付くのかをよく観察し、捉えることが大事です。
とはいえ、小学校低学年のうちから具体的に捉えることは難しいです。最初は頭を大きな丸、胴を大きな四角、足は細長い四角を4つというようにシンプルに捉えられるようにしましょう。そして、ライオンの最大の特徴のたてがみをつけてあげれば、ちゃんとライオンに見えますよ。

低学年のうちはとにかく「パーツと特徴を捉える」ことを意識しましょう。それが身につけば、「お腹には丸みがあるな」「太ももは大きく張っているんだな」ということに少しずつ気づき、絵に反映させられるようになってきます。

















