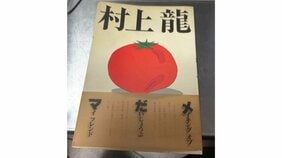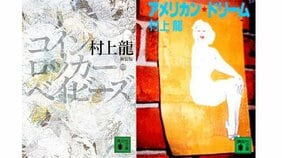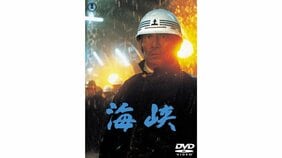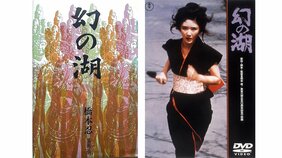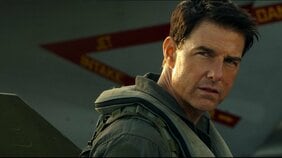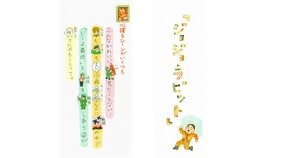1982年、17歳の私に灼きついた映画とは
断っておきますが、私の仕事は映画を作ることです。
料理も作らず飽食の限りを尽くす料理人は料理人とは言えません。だから私が映画を語るなんてもってのほかです。ひと様が作った映画についてしたり顔で講釈垂れたりとか何様だよと思うし、「そもそもそんな暇あったら映画作れ、あるいは作った映画をより良くしろ」と我が内なる声が叫ぶわけです。
だけど、結局のところ映画だけで育ってしまった人間の悪癖で、話題といえば映画のことばかり。映画のことしか語れません。しかもこれから作る映画のことについてはあまり積極的に語れません。語って聞かせたり読ませたりするよりも、出来上がった映画を観てもらいたいからです。
また、今まで自分で作ってきた映画をあれこれ補足するように語っても、どこか言い訳じみてしまうので、これまた観ていただくのが一番です。じゃあ、何の話ができるのか。
仮に歴史に名を残す映画があったとしましょう。続編も作られる、あるいはリメイク、リブート。挙げ句の果てにフランチャインズ。そもそも映画とは、独創的表現で彩られた芸術でありながら、大規模な投資で更なる利益を回収せんと策謀の限りを尽くす商品開発ともいえるのです。そんな相反する二面性をもちながら、いかなる形で名を残すか。というよりも個人の記憶に残るのか?
とはいえ、私の歴史はそんな映画というものだけで積み上がってきた。 とりわけ高校2年生の1年間で観た映画は、私にとって大きな爪痕のような影響をもたらしている。最近そう実感しているのです。
その1年に集中した作品は、ただ観るだけにとどまらず、どうやって作られたのか、果ては自分だったらこう作る、それのほうが遥かに面白いのではないかと私に考えさせたものぞろい。 ひいては今の立ち位置に私を導いてしまった映画ばかりなのです。
あの時これらの映画に出会わなかったら、今頃はもっと真っ当な人生を歩んでいたに違いない。けれども、決して後悔はしていないとだけ言えます。
そんな我が人生を壊した映画たちとの1年。 西暦1982年。昭和57年のことであります。
まずは、1月23日に観たウォルフガング・ペーターゼン監督『U・ボート』(1981)。 今年8月に81歳で亡くなった監督の、40歳でのデビュー作です。