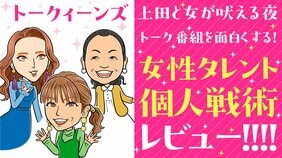「粗品対策」の噂も出た『オールスター感謝祭』
先日の『オールスター感謝祭』(TBS)。多くの人からクイズ問題の傾向が変わったという感想があった。
クイズ作家の方が交代になったというのもあるだろうが、確かに、これまでのような時事問題中心から、比較的一般常識を問うような問題が増えたように思う。
そこで、まことしやかに囁かれているのが「霜降り明星の粗品が勝ちすぎているから、対策したのではないか」という噂である。
実際のところは、おそらくそれが理由ではなく、より視聴者が楽しめる内容を追求した結果なのだろうが、そういう噂が出るくらいにここ数回、粗品は勝ちまくっていた。
そもそも、『オールスター感謝祭』自体がクイズを真剣にやる番組というよりは、マラソンやアーチェリーをはじめとする各ゲームで盛り上げ、新番組や人気番組をアピールするというTBSのお祭りである。
賞金がもらえるというメリットはあるが、仮にクイズで総合優勝したとて、おめでとうムードは数秒で、あっという間に番組はフィナーレである。
そこを敢えてむやみやたらに真剣にクイズに打ち込むという面白さを追求してきたのが、ここ最近の粗品であった。時事中心に予習をガッツリ行い、ひっかけ問題や早押しにもしっかり対策をして臨んだ結果、前回までにピリオドチャンピオンになること9回、2022年春にはついに総合優勝も果たした。
しかし今回クイズ傾向が変わったことで、粗品の総合順位は12位と大きくランクダウン。意地でピリオドチャンピオンは1回奪還したが、それが精一杯だった。
実際に『オールスター感謝祭』が粗品対策をしたのかはわからない。しかし世の中には圧倒的に強い人が出てくると白けてしまうと考える人は多い。
白熱のつばぜり合いで一体誰が勝つんだ?という勝負が見たいのであって、事前に対策をした人が圧勝していく様子は一回はいいとしても、繰り返されると「なんだよ、つまんね」となりがちである。
そういった状況になると、運営側はあの手この手で接戦になるように工夫する。