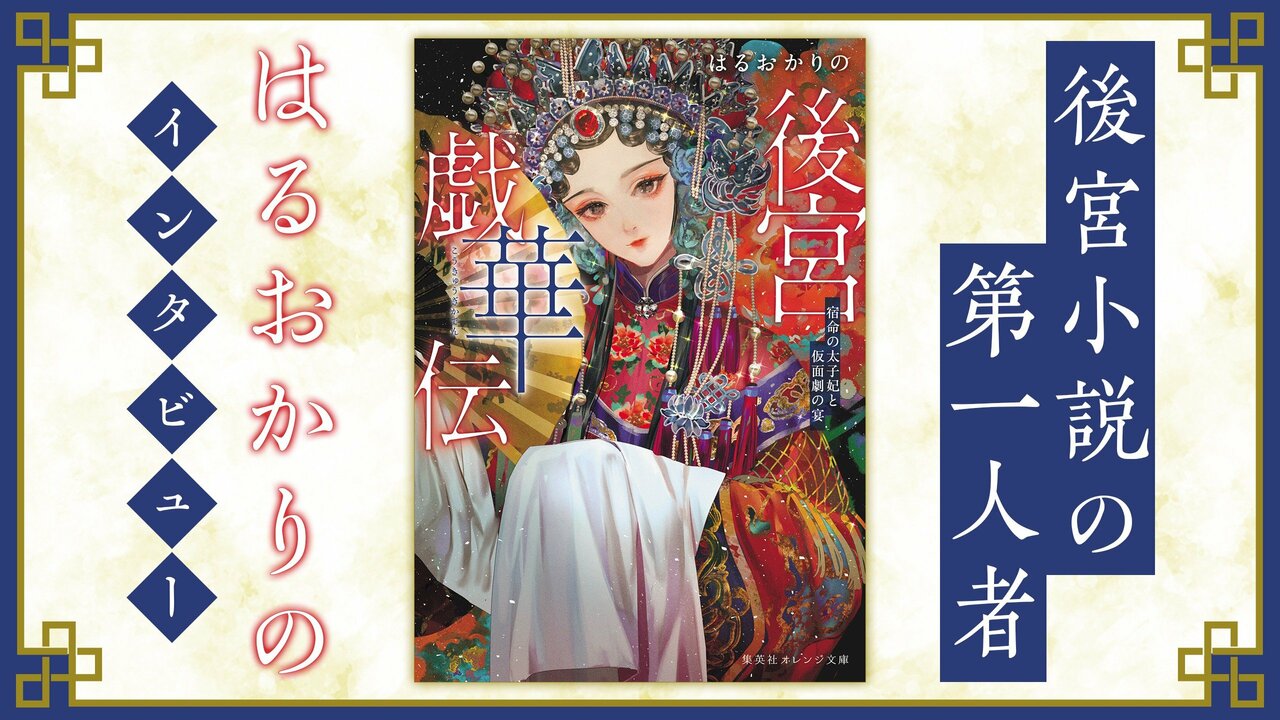後宮に現代の価値観を持ち込まない
――凱王朝の詳細な年表や、宗室・高一族の家系図が作られているように、「後宮史華伝」シリーズには架空の歴史ものとしても楽しめる奥行きがあります。『後宮詞華伝』の時点では続編は構想されていなかったそうですが、どのタイミングで凱王朝の歴史や系譜が固まったのでしょうか。
第1部第1巻『後宮詞華伝』は読み切りのつもりで書いたので、物語の展開に必要な設定しか作っていません。王朝の背景を意識して書くようになったのは第3巻『後宮錦華伝』ですね。ヒロインが未来でどういう立場になっているかについて書いたのがはじまりです。ただ、凱王朝の骨格をしっかり描写するようになったのは第5巻『後宮幻華伝』からです。「後宮史華伝」シリーズの最終的なゴールを意識しはじめたのもこの巻でした。
後宮と題しながら、第4巻までは皇帝と妃を主役に置くことを避けていました。皇帝がヒーローだと、どうしてもヒロイン以外の女性を娶ることになるので、少女向け小説の読者には受け入れがたいかな……と遠慮していたんです。思い切って書いてみた結果、いまの「後宮史華伝」シリーズがあるのだと思います。一夫多妻制は甘い恋愛を描くには不向きですが、後宮の実態を描くには避けてはとおれない要素ですので。
とはいえ、『後宮幻華伝』で書いた夜伽の手順は少女向け小説の読者に配慮してだいぶやわらかい表現にしたものでした。より史実に近づけた夜伽の作法は第2部第1巻『後宮染華伝』で描写しています。その点でいえば、『後宮幻華伝』は『後宮染華伝』のプロトタイプですね。
――皇帝の世継ぎを産む役割をもつ後宮では、皇后や妃嬪(ひひん)など多数の女性が階級制度の中で暮らしており、選ばれた人が皇帝の閨に侍って夜伽をします。一夫一婦制の現代日本とは価値観やリアリティが異なる設定の中で愛の物語を描くにあたり、大切にされている、あるいは気をつけていることはありますか?

いちばん気をつけているのは、現代の価値観を持ちこまないようにすることですね。できるだけモデルにしている時代の価値観で語るようにしています。
たとえば皇帝がヒロインを溺愛するあまり、後宮を解散してヒロインだけを一生誠実に愛するという結末はいかにも女性の夢という感じですが、歴史の視点から見ると褒められたことではありません。
明王朝に弘治帝という皇帝がいます。彼の後宮には張皇后がいるだけで、ほかに妃はいません。張皇后が産んだ二人の皇子のうち一人は夭折してしまい、無事に成長したもう一人の皇子が正徳帝として天下に君臨しますが、この方はかなりハチャメチャな皇帝でして、明王朝をひっかきまわしたトラブルメーカーのひとりです(万暦帝というもっとすごい人があとで登場しますが……)。しかも彼は世継ぎを残さず崩御するので、皇統は傍系に移ってしまいます。この皇位継承劇は正徳帝のあとを継いだ嘉靖帝の御代に大礼の議なるややこしい政争を引き起こし、のちのちまで禍根を残す結果になります。皇帝が浮気(?)をしなかったことが王朝の屋台骨を揺るがす大問題に発展してしまったわけです。
――現代人の感覚からすると、一人の妻を愛しぬいた弘治帝と張皇后の関係はロマンチックに思えます。ですが、結果的に大きな問題を引き起こしたのですね。
弘治帝は張皇后にとっては誠実なよき夫だったでしょうが、それも生前の話です。嘉靖帝が伯母である張皇后よりも生母を敬うようになったため、張皇后の晩年はたいへん不遇だったといわれています。もし弘治帝が妃嬪とのあいだに皇子をもうけていて、嘉靖帝ではなくその皇子が即位していれば、張皇后は嫡母(父親の正妻)として敬われたでしょうに……。皇帝の嫡母と生母が対立することはよくあるので一概にはいえませんが、生母が亡くなっているケースなら嫡母のひとり勝ちですから、庶出の皇子がいれば幸福な晩年になる可能性はあったのです。しかし、弘治帝は張皇后以外と子をもうけていないので最初からその道は断たれているわけですね。こう考えると、弘治帝が張皇后にとってほんとうに「よき夫」だったのかも怪しくなってきます。
ご先祖様から受け継いだ王朝と愛する張皇后。弘治帝はふたつながら不幸にしてしまった……といったら、弘治帝に意地悪すぎるでしょうか。

――そのように考えると、弘治帝の愛も別な見え方になってきますね。
皇帝という最上級のハイスペック男性に一途に愛されるのはたしかに女性にとって憧れかもしれませんが、彼が捧げてくれるひたむきな愛情は恐ろしいほどの重責と抱き合わせになっています。なぜなら皇帝には多くの子をもうける義務があるからです。皇帝の唯一の妻になる人は王朝のためにかならず世継ぎを産まねばなりません。中国史の場合、世継ぎは男子限定です。女子をいくら産んでもだめなんです。生まれる子の性別を選べないこと、出産が命にかかわる大仕事であること、生まれた皇子が夭折してしまうかもしれないこと、無事に成人しても後継者の素質をそなえていないケースもあることをふまえれば、皇帝の唯一の妻という立場はロマンチックな恋愛物語が描く甘いハッピーエンドとは似ても似つかない、新たにはじまる苦難の第一歩といってもいいでしょう。