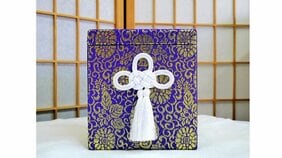知らないと火葬場でショック! 東西で異なる拾骨事情
2022年秋に京都市が、“残骨灰(火葬後に残る微細な骨や灰)”から見つかる金やプラチナなどの有価金属を抽出・精錬して売却したことで得られる見込額は1億円超”になるとしたことがニュースになった。
しかし、『中國新聞』(2019年12月13日掲載)によると、横浜市、仙台市、浜松市、名古屋市など、一部の政令都市ではすでに残骨灰を売却している。取材中に得た知識で〈残骨灰 入札〉で検索したところ、福岡市、岐阜市、下関市、横須賀市など多くの都市で同様のとりくみが実施されていることがわかった。
コロナ禍の観光客減により、財政難とされる京都が売却益を得ることで注目されたのか、ネットでも話題になっていた。そこで不思議に思ったのは、「個人資産じゃないの?」や「羅生門の老婆みたい」と感情的なコメントを書く人がいる一方、西日本在住らしき人は「割り切り方の問題かも」や「リサイクルは当然」とクールだったりする東西の温度差だ。
これを端緒に調べた東京出身・在住の記者は驚いた。「東日本は全部拾骨」、「西日本は部分拾骨」と火葬後の骨上げの仕方が大きく異なっていたからである。そこで、浄土宗の僧侶で京都・正覚寺住職でジャーナリストの鵜飼秀徳さんにその違いを聞いた。
「西日本は、火葬したあとにすべてのお骨を拾わず、多くの遺骨を火葬場に残すため、残骨灰のことの想像がつきやすく、それが残骨灰売却に対する反応の差になったのではないでしょうか。
葬送儀礼は地域性が大きく、拾骨に関して、関東はすべてが当たり前、関西は部分。そのため、骨壷も関東は7寸(直径約21cm)、関西は3~5寸(9~15cm)と異なります。また、関東は納骨室に骨壷ごと収めますが、関西では納骨の際に骨壷から遺骨をさらしの袋に移し、土に還しやすい埋葬法をとります」