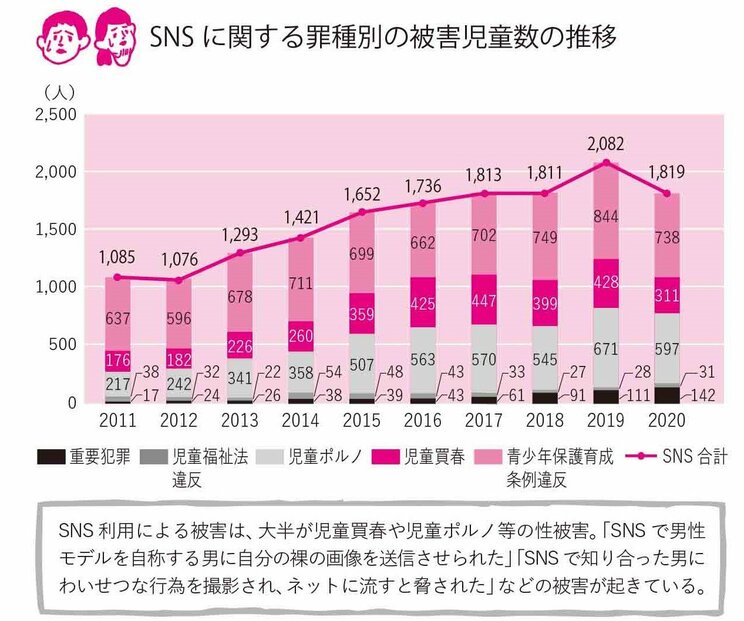SNSなんてしないほうが精神的にラク
学校で長期休暇前にプリントや口頭で、SNSやインターネットの利用に関する注意喚起を受けたことがある人は多いかもしれません。私もギリギリその世代です。実際、トラブルに巻き込まれることを防ぐために、「SNSやインターネットは危険」と教えたり、そもそも利用を制限したり、禁止したりする学校も多いはずです。
私が生徒の立場であれば余計なお世話と思うでしょうが、今の立場からだと、インターネットは別として、家族など信頼できる限られた関係の中から少しずつ関係を広げていくような使い方がベストだと考えます。
ネット上での「人づきあい」がわかっていない状態のまま、急速につながりを増やすことは、やはりリスクしかないでしょう。本当に信頼している人にしか、アカウントを教えないなど、ルールを事前に決めておくといいかもしれません。
たとえば、友だちの悪口を目にしたことはありませんか? 心がザワつきますよね。
仮にクラスメイトからSNSのアカウントを聞かれても、「持ってない」「親にダメだと言われている」「あんまり見ないから無視しちゃうかも」などと言って、一定の距離感を保って接するのは、大人なカッコいいコミュニケーション術です。もちろん、こんなふうに「自分は自分、他人は他人」と割り切るのはとても難しいでしょうが……。