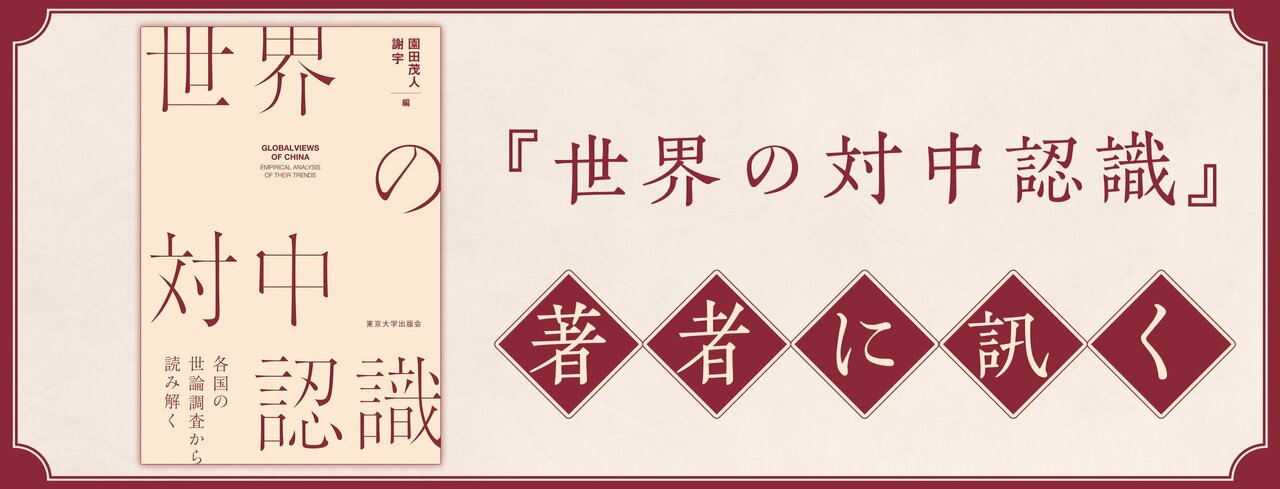人々の対中認識の源泉はいくつかの要素に分解できる
――どんなことが人々の対中評価に関係してくるのでしょうか。
園田 たとえばアジア太平洋地域における中国台頭への認識・評価には、 1.経済、 2.国際環境、 3.社会・文化、 4.政治とメディア、という4要因が関わっています。
まず、1つ目に中国と「経済」的なつながりが強い国の方が、また経済危機の際に支援を受けていたほうが肯定的になります。
2つ目の「国際環境」とは、たとえばその国が中国と領土紛争を抱えていたり、アメリカや日本と同盟関係があったりすると否定的な人が増える傾向があり、逆にアメリカと関係が冷え込む要因があると肯定的になる傾向があります。
3つ目の「社会・文化」とは、華人を多く抱えていたり、中国による文化支援で益があると思うと肯定的になり、香港人意識や台湾人意識といった華人の ローカルアイデンティティが強まると否定的な傾向が強まります。
4つ目の「政治とメディア」とは、対中政策が親中国的な国の人々は肯定的になる傾向があり、民主主義が発展している国では否定的な傾向があります。
――それらが絡み合っているわけですね。「経済」に関係する部分だと思いますが、資源をめぐる紛争などに陥りやすいこともあって「隣合っている国同士は基本的に好意的に見ない」という指摘も本にありました。たしかに日本と中国ももっと離れていたら別に揉めないだろうなと感じます。
園田 そうですね。たとえばアジア諸国はおおむねアメリカには肯定的な一方、中国には否定的な傾向があります。逆に一部のラテンアメリカ諸国には根強い反米感情がある一方で、中国は2000年代前半からラテンアメリカに積極的に投資をしていることもあって肯定的に捉える国が少なくありません。
自分が重視しているものを持っているかどうかで、相手の評価が左右される
――国としての傾向だけでなく、ひとつの国の中でも意見の違いが同様の要因で説明できますか。
園田 ええ。ひとつは政治的理念が関係しています。例えばアメリカでは共和党支持か民主党支持かによって、米中貿易摩擦に対する評価が異なります。日本の大学生に対する調査では、理系は中国評価が高いんですね。理由を探ってみると、彼らは日本と比べて電子決済やスマホを使った意思決定、インフラが発展していることを肯定的に捉えている。一方で文系は政治体制や文化を見ていて理系のように「中国に学ばないと」という度合いが強いとは言えない。つまり、自分たちが重要だと考えるものが相手にあるかないかで評価が変わってくる。
――なるほど、他者に自分の関心を投影していると。
園田 これは報道のフレームも同様です。メディアが何を重視したフレームを用いるかによって私たちの考えが誘導されてしまうことには意識的になった方がいい。メディアの報道が自分たちの目であるかのような感覚があるなら、まずは疑ってみる。いったいどんな特徴があるかを一歩下がって見る必要があります。
これは今回のロシアのウクライナ侵攻をめぐる問題についても言えます 。自分たちがなぜそう考えるのかを反省的に捉えると同時に、相手にはなぜそう見えているのかという視点も持ちたい。こう言うと「相手の側に付くのか」と言われてしまうのですが、そうではなく、自他の視点、視座を確認する、ということです。それぞれ見ている場所が違いますから。
そこから始めないと互いに「なぜこちらの言うことを聞かないんだ」という怒りをぶつけ合って終わってしまうだけです。