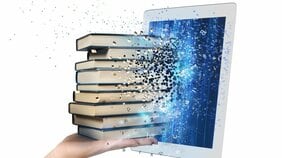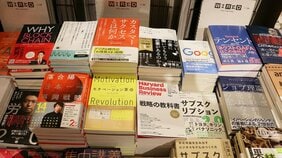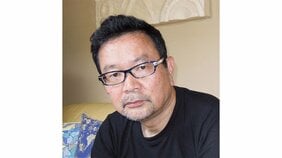新聞を小説のように読む必要はない
まず大切なポイントは、メディアに触れるときは常に二つの「読み方」を使い分けることです。
ひとつ目は「ブラウジング」で、長い文章やページ全体にざっくり目を通すこと。テキストを前から順に読むのではなく、全体を俯瞰(ふかん)して「何についての話なのか」「どういうことが書いてあるのか」といった要旨をおおまかにつかむのが目的です。
たとえば経済誌のオピニオン記事なら「日本の財政についての話で、この人は××のリスクを訴えている」といったこと。過去にたくさん読んだ経験がある分野であれば、どんなキーワードが含まれているかだけで趣旨を把握できるので、ブラウジングは楽になります。
そして、二つ目が「リーディング」です。こちらは国語の授業のように、前から 順に意味を把握しながらきっちりと進んでいく読み方。小説はもちろんノンフィクションでもこちらのやり方がほとんどでしょう。知識や情報を得るために新書やルポルタージュを手に取るようなケースでは、全部リーディングではなく、「ここはべつにいいか」という部分だけブラウジングを使って、駆け足で読み進めたりするケースもあるかもしれません。
本章では、前者の「ブラウジング」の技術を中心に扱います。というのも、本書で語っているような知識や情報のコンテンツはすべて、まずブラウジングするべきものだからです。
最初にざっと目を通して「そのままお別れするもの」と「リーディングして一部を頭に残すべきもの」に分ける。言うまでもなく大量の情報をさばけるのはブラウジングであって、はじめからすべてをすべてリーディングするのは不可能です。
「朝刊の文字数はおよそ20万字。新書の2冊分の情報が詰まっている(東洋経済オンライン『池上彰が解説「今さら聞けない新聞の読み方」』)」と言うように、すべての記事にしっかり目を通していたら生活できません。